今日3月30日は、オランダの画家フィンセント・ファン・ゴッホの誕生日です。1853年のこの日、後に「ひまわり」や「星月夜」などの名画を残し、印象派と表現主義の架け橋となる偉大な芸術家が生まれました。生前はほとんど評価されず、経済的にも苦労したゴッホですが、死後、その芸術性は高く評価され、現在では世界で最も有名な画家の一人となっています。彼の生涯は、真の価値が時に見過ごされることの象徴とも言えるでしょう。
こんにちは、朝日楼(あさひろう)です。
ゴッホのように生前は評価されなかったものの、後世にその真価が認められた例は歴史上少なくありません。今日の日本では、私たちの生活の根幹を支える農業、特に米作りの価値が十分に認識されていないのではないでしょうか。最近、「令和の百姓一揆」と呼ばれる農家の抗議活動が注目を集めています。この現象は、私たちの食卓と直結する重要な問題を提起しています。
「令和の百姓一揆」とは何か
2023年から2024年にかけて、全国各地の農家が集まり、農産物の価格低迷や生産コスト高騰に対する抗議活動を行っています。これが「令和の百姓一揆」と呼ばれるものです。特に米農家の窮状は深刻で、米価の下落が続く中、肥料や燃料などの生産コストは上昇し、多くの農家が経営の危機に直面しています。
2023年11月には東京・日比谷公園に全国から約5,000人の農業者が集結し、農産物の適正価格での取引や生産コスト上昇への対応を求める大規模な集会が開かれました。参加者たちは「このままでは日本の農業は崩壊する」「食料安全保障の危機だ」と訴えました。
歴史を振り返ると、江戸時代の百姓一揆は年貢の減免や悪政の改革を求めるものでした。現代の「令和の百姓一揆」は形こそ違えど、生産者が適正な対価を得られない構造的問題に対する抗議という点で共通しています。
日本の食料自給率の危機的状況
日本の食料自給率(カロリーベース)は2022年度で38%と先進国の中でも極めて低い水準にあります。これは先進国の中でも最低レベルであり、G7諸国の中では最下位です。比較すると、フランスは約130%、アメリカは約130%、ドイツは約95%、イギリスは約70%となっています。
特に主食である米の自給率は減少傾向にあり、現在は約97%です。一見高く見えますが、これは消費量自体が減少している影響も大きく、生産基盤は弱体化しています。米以外の穀物自給率はさらに低く、小麦は約15%、大豆は約7%に過ぎません。
食料は国民生活の根幹を支えるものであり、その自給率の低さは国家安全保障上も大きな課題です。世界的な気候変動や国際情勢の不安定化により、食料輸入が滞る可能性も否定できません。実際、2022年のロシア・ウクライナ紛争は世界の穀物市場に大きな影響を与え、食料安全保障の重要性を再認識させました。
そのような事態に備え、生活必需品の自給率を高く保つことは国策として重要です。食料は石油や天然ガスと異なり、いざという時に備蓄だけでは長期的な対応ができないという特性があります。
米価格の構造と生産者の収益
現在の米価格は本当に生産者に適正な利益をもたらしているのでしょうか。米の小売価格の内訳を詳しく見てみましょう。
例えば、スーパーで5kg2,000円程度で販売されている米の場合:
- 生産者手取り:約900円(45%)
- 流通経費・マージン:約700円(35%)
- 卸売業者マージン:約300円
- 小売店マージン:約400円
- 精米・包装コスト:約300円(15%)
- 精米コスト:約150円
- 包装材費:約100円
- 物流コスト:約50円
- 税金など:約100円(5%)
しかし、この生産者手取りからさらに以下のコストが差し引かれます:
- 種もみ代:約50円
- 肥料代:約150円(近年は国際情勢により約1.5倍に高騰)
- 農薬代:約100円
- 機械の減価償却費:約200円(トラクター、田植え機、コンバインなど高額な機械が必要)
- 燃料費:約100円(これも近年高騰)
- 水利費:約50円
- 土地代(自作地でない場合):約100円
- 人件費(雇用がある場合):約100円
これらを差し引くと、5kgあたりの純利益は約50〜150円程度になることも珍しくありません。10aあたり500kg程度の収穫があるとして計算すると、年間の純利益は5万〜15万円程度。これでは専業農家として生計を立てることは困難です。
さらに、気候変動による自然災害のリスクも増大しており、台風や豪雨による冠水、猛暑による高温障害など、収量や品質に影響を与える要因も増えています。これらのリスクに対する保険料も農家の負担となっています。
米価下落の背景と構造的問題
米価下落の背景には複数の要因があります:
- 消費量の減少: 日本人の米の年間消費量は1962年の118kgから2022年には約50kgと半分以下に減少しています。食の欧米化や多様化により、パンやパスタなど小麦製品の消費が増加し、米の需要が減少しています。
- 輸入米の増加: ミニマムアクセス米(最低輸入義務量)として年間約77万トンの外国産米が輸入されています。これはWTO(世界貿易機関)協定に基づくもので、国内生産量の約8%に相当します。この輸入米の多くは加工用や援助用に回されていますが、国内市場への影響も無視できません。
- 生産調整の限界: 1970年代から続く減反政策による生産調整が行われていますが、需給バランスの適正化には至っていません。2018年からは行政による生産数量目標の配分が廃止され、民間主導の需給調整に移行しましたが、その効果は限定的です。
- 流通構造の問題: 多段階の流通過程で中間マージンが発生し、生産者の手取りが減少しています。特に系統出荷(JA経由の出荷)では、複数の段階を経ることで価格が上乗せされていきます。
- 小売業界の価格競争: 大手スーパーやディスカウントストアの価格競争により、米の小売価格が押し下げられる傾向があります。特売品として安価な米を提供することで集客を図る戦略が、米の価値を下げる一因となっています。
- 農業政策の転換: 2018年以降、米政策の市場原理への移行が進み、政府による価格支持政策が弱まっています。これにより、米価の変動リスクが農家に直接影響するようになりました。
農家はどのように生計を立てているのか
では、このような状況下で農家はどのように生計を立てているのでしょうか。
- 兼業化: 多くの稲作農家は他の仕事と兼業することで生計を立てています。農林水産省の調査によれば、稲作農家の約7割が兼業農家です。会社員や公務員として働きながら、休日や早朝・夕方に農作業を行うというパターンが一般的です。
- 経営の多角化: 米だけでなく、野菜や果物など高収益作物を組み合わせたり、直売所や農家レストランなど6次産業化に取り組む農家も増えています。例えば、米農家が加工品(おにぎり、米菓子など)の製造販売に乗り出したり、農家民宿を経営するケースも見られます。
- 規模拡大: 小規模農家が減少する一方で、大規模経営体が農地を集約し、効率化によってコスト削減を図っています。100ヘクタール以上の大規模経営体では、スケールメリットを活かして収益性を確保しているケースもあります。
- 補助金への依存: 各種農業補助金が農家経営を下支えしている面も否定できません。水田活用の直接支払交付金や環境保全型農業直接支払交付金など、様々な補助金制度があります。しかし、これは根本的な解決策とはいえません。
- 高齢者の年金収入: 農業従事者の平均年齢は67歳を超えており、年金収入と組み合わせて生活している農家も少なくありません。これは農業の持続可能性という観点からは大きな問題です。
- 特別栽培米や有機米などの高付加価値化: 慣行栽培よりも手間はかかりますが、有機栽培や特別栽培などの付加価値をつけることで、高価格での販売を実現している農家もいます。消費者との直接取引や固定客の確保により、安定した収入を得る戦略です。
- 農業法人化による経営効率化: 個人経営から法人経営に移行し、税制面でのメリットを活かしたり、雇用の安定化を図る動きも広がっています。
江戸時代からの農民の位置づけと歴史的変遷
「百姓が貧しいのは江戸時代からの流れなのだろうか」という問いについて考えてみましょう。
江戸時代、農民は武士、農民、工人、商人という身分制度の中で、武士の次に位置づけられていました。「農は国の本なり」という考え方があり、表向きは重視されていました。しかし実際には、年貢の負担は重く、凶作時にも容赦なく徴収されることが多く、農民の生活は厳しいものでした。
年貢は収穫の4〜5割に達することもあり、さらに村の運営費や冠婚葬祭の費用なども必要でした。このような厳しい状況に対して、農民たちは時に一揆を起こして抵抗しました。江戸時代の記録には3,000件以上の一揆が記録されています。
明治以降も、地租改正や産業革命の中で、農業は工業化の資金源として位置づけられ、農民の負担は軽減されませんでした。地租改正により、それまでの年貢に代わって金納の地租が課されましたが、その負担は依然として重いものでした。
大正から昭和初期にかけては、小作争議が頻発しました。当時の農村では地主制が発達し、小作人は収穫の5〜7割を小作料として支払わなければならない状況でした。
戦後の農地改革で自作農が増えましたが、高度経済成長期には農村から都市への人口流出が進み、農業の地位は相対的に低下しました。1961年に制定された農業基本法は、他産業との所得格差の是正を目指しましたが、結果的には兼業化を促進することになりました。
1990年代以降のグローバル化の波の中で、農産物の輸入自由化が進み、国内農業は国際競争にさらされるようになりました。1995年のWTO発足、各国とのEPA(経済連携協定)やTPP(環太平洋パートナーシップ協定)などにより、農業保護政策は徐々に縮小されてきました。
このような歴史的経緯を見ると、農業・農民の社会的・経済的地位の低さには一定の連続性があると言えるでしょう。しかし、それは宿命ではなく、政策や社会構造によって形作られてきたものです。
世界の農業政策との比較
日本の農業政策を他国と比較してみましょう。
EU: 共通農業政策(CAP)のもと、食料安全保障や環境保全、農村地域の活性化を目的とした直接支払制度が充実しています。農家所得の約4割が補助金によって支えられています。特に注目すべきは、環境保全や生物多様性維持などの「公共財」を提供する農業の多面的機能に対して支払いを行う仕組みです。
フランス: EUの共通農業政策に加え、独自の農業保護政策を実施しています。例えば、「農業経営継承法」により若手農業者の参入を促進し、農地の細分化を防止しています。また、「食品ロス対策法」により、大型スーパーが売れ残った食品を廃棄することを禁止し、フードバンクへの寄付を義務付けています。
アメリカ: 農業法に基づき、価格変動に対応するための収入保険や不足払い制度が整備されています。また、バイオ燃料政策によるトウモロコシ需要の創出など、農産物の新たな用途開発も進んでいます。アメリカの農業支援額は年間約200億ドル(約2.2兆円)に達し、特に穀物農家への支援が手厚くなっています。
韓国: 米の価格支持政策や直接支払制度が充実しており、食料自給率向上を国家目標として掲げています。特に米については、政府が市場価格を監視し、価格が下落した場合には買い入れを行う制度があります。また、若手農業者の育成にも力を入れており、就農支援金や低利融資制度が充実しています。
スイス: 国土の保全や景観維持など、農業の多面的機能を高く評価し、直接支払制度による手厚い保護を行っています。農家所得の約7割が政府からの直接支払いによるものとされ、その代わりに厳格な環境基準の遵守が求められています。
これらの国々と比較すると、日本の農業支援策は十分とは言えない面があります。特に食料安全保障の観点からの戦略的な取り組みが不足しています。日本の農業予算は年間約2兆円ですが、その内訳を見ると生産基盤の整備や災害対策などのインフラ整備に重点が置かれ、農家の所得を直接支える政策は限定的です。
持続可能な農業のために必要な対策
「令和の百姓一揆」が示す問題を解決し、持続可能な農業を実現するためには、以下のような対策が考えられます。
- 適正価格の実現: 生産コストを反映した適正な価格形成メカニズムの構築が必要です。例えば、最低価格保証制度の導入や、流通の効率化による中間マージンの削減などが考えられます。具体的には、生産費調査に基づく価格下限の設定や、不当な買いたたきを防止する法整備などが挙げられます。
- 直接支払制度の拡充: 食料安全保障や環境保全など、農業の多面的機能を評価した直接支払制度を拡充すべきです。EU型の所得補償制度を参考に、農家の基礎的な所得を保障する仕組みを整備することで、安定した経営環境を提供できます。また、環境保全型農業や有機農業に取り組む農家への特別な支援も重要です。
- 若手農業者の支援強化: 新規就農者への資金援助や技術指導の充実、農地取得の円滑化など、若い世代が農業に参入しやすい環境整備が必要です。例えば、農地バンクの活用による土地集約化や、ITを活用したスマート農業技術の普及促進などが挙げられます。
- 技術革新の促進: スマート農業やAI、ロボット技術の導入支援により、生産性向上とコスト削減を図るべきです。具体的には、自動運転トラクターやドローンによる作物管理など、最新技術を活用した効率化が期待されています。
- 食育と国産農産物の価値再評価: 国民に対する食育を通じて、国産農産物の価値や重要性を再認識してもらう取り組みが必要です。学校給食で国産食材の使用を推進するほか、地元産品を積極的にPRするキャンペーンも有効でしょう。
- 流通構造の改革: 生産者と消費者を直接つなぐ流通チャネルの開発や、フードチェーン全体での公正な利益配分の仕組みづくりが求められます。例えば、生産者直売所やオンラインマルシェなど、生産者が直接販売できる場を増やすことが重要です。
- 国民的議論の促進: 農業政策は国民全体で議論されるべきテーマです。食料自給率向上や生産者支援について広く意見交換し、社会全体で解決策を模索する姿勢が求められます。
消費者としてできること
私たち消費者にもできることがあります:
- 国産農産物を意識的に選ぶ: 少し高くても国産、特に地元の農産物を選ぶことが生産者支援につながります。地元で採れた旬の食材は鮮度も高く、美味しいものが多いです。
- 食品ロスの削減: 買いすぎや作りすぎを避け、食材を無駄にしないことで間接的に農業を支援できます。家庭でできる小さな取り組みでも、大きな影響につながります。
- 生産者との交流: 農家直売所や農業体験などを通じて生産者と交流し、農業への理解を深めることが大切です。生産者との会話から学ぶことは多くあり、食材への愛着も増します。
- 適正な価格への理解: 安さだけを追求せず、適正な価格で農産物を購入することの意義を理解しましょう。適正価格は生産者が持続可能な経営を行うために必要不可欠です。
最後に:食の安全保障は国の礎
日本の農業、とりわけ米作りは単なる産業ではなく、国民の命と文化を支える重要な基盤です。「令和の百姓一揆」は、この基盤が危機に瀕していることへの警告と捉えるべきでしょう。
食料自給率向上と生産者が持続的に営農できる環境整備は、日本社会全体で取り組むべき課題です。歴史的にも、農業が衰退した国家は長く存続できませんでした。私たち一人ひとりが食と農業問題に関心を持ち、小さな行動から始めることで未来は変えられるはずです。
ゴッホが生前評価されずともその価値が後世に認められたように、日本の農業も今こそその真価を見直し、大切に守っていくべき時ではないでしょうか。日本の豊かな食文化と農業の伝統は私たち自身だけでなく次世代にも引き継ぐべき宝物です。
それではまた次回の記事でお会いしましょう!

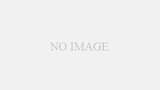
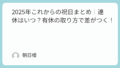
コメント